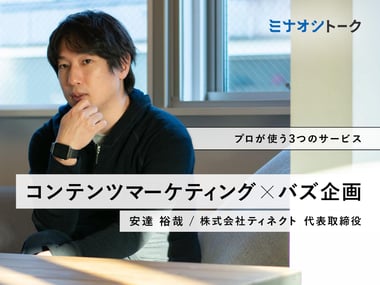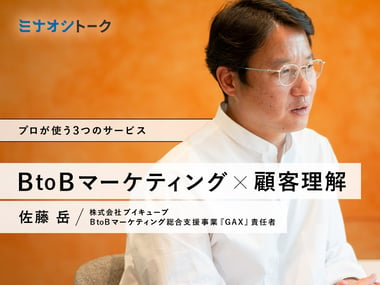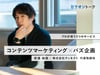「成果を最短で出すことに注力する」オウンドメディアの立ち上げ時にプロはどう考えるのか
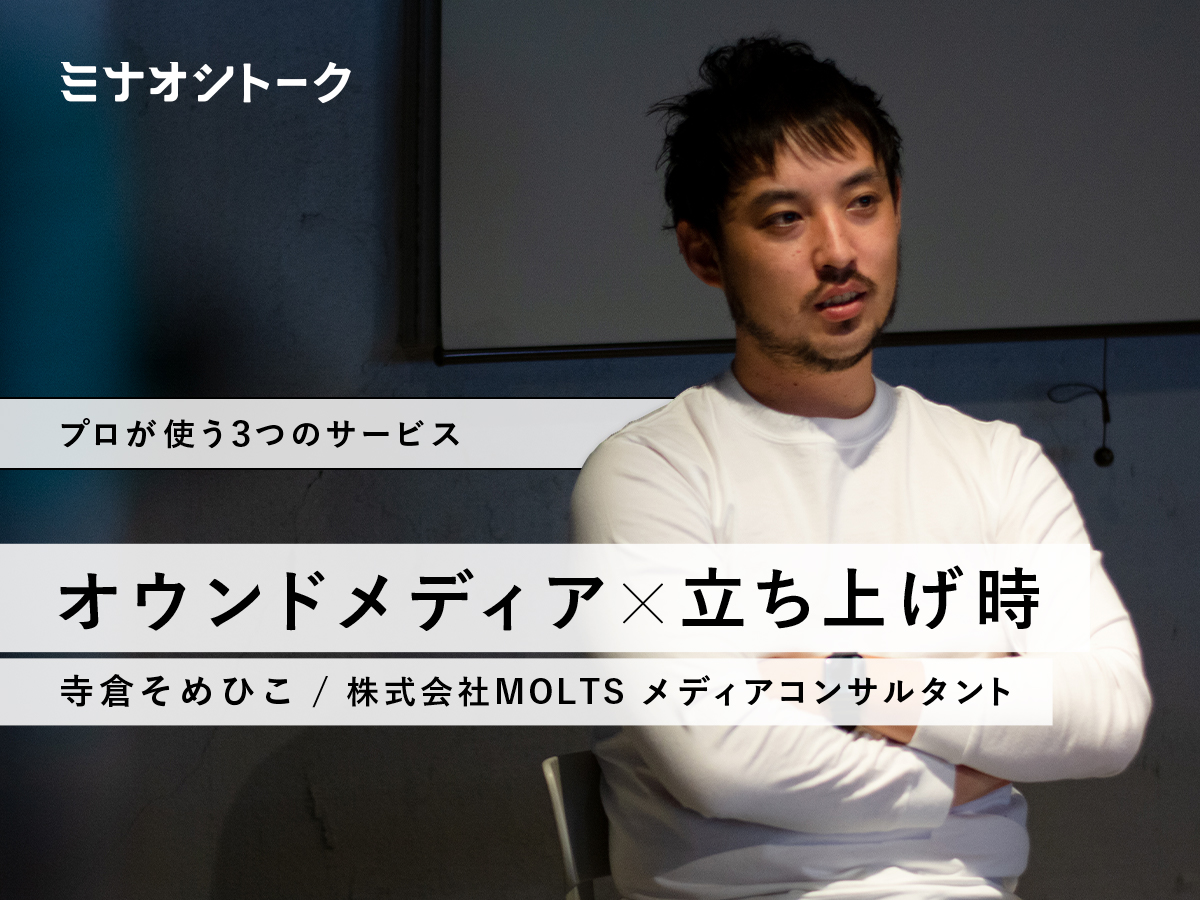
ーー 結果を出すのでなく、その手前にあるデータで見える成果を最短距離で出せるようにコンサルティングしています。
オウンドメディア最盛期とも言える2013年に株式会社LIGへ入社し、マネージャーとしてオウンドメディアのグロースやマネタイズ、さらにメディアを起点とした新規事業開発などを推し進め、2016年3月にはデジタルマーケティングカンパニー『MOLTS』を設立した寺倉そめひこ氏。
ある案件ではゼロから立ち上げて3年で四半期で億単位の利益創出に貢献、また別の案件ではリード獲得数をわずか3ヶ月で4,000件へと倍増、さらに別案件ではテレアポを中心としたアウントバウンドカルチャーが強い1000名を超える企業にインバウンドカルチャーを浸透させていく土台を作る(下記にて記載有)など、累計50社以上のクライアント企業の事業成長にコミットし続けてきたオウンドメディアマーケティングのプロフェッショナルである。
今回、そんな寺倉そめひこ氏に、オウンドメディアの立ち上げ時に大切にしている考え方や、日々自身が活用しているというツールについて語っていただいた。
オウンドメディア立ち上げ前に大切にしている2つの考え方
私は、オウンドメディアを “企業の事業・組織課題を解決する手段としてのメディア” として位置付け、より企業の事業成長に貢献させるためにはどうすればいいのかという観点を前提に考えています。また、本来のオウンド(自社の)メディア(媒体)という観点から、コーポレートサイトをはじめ、広く自社所有である媒体の総称をオウンドメディアと呼んでいます。
そんな私が大切にしている考え方のひとつに、 “オウンドメディア” だけで考えない、ということがあります。オウンドメディア領域でこれまでに数多くのご相談をいただいてきましたが、クライアントの要望に応え、オウンドメディアを立ち上げ、成長させることが、必ずしもクライアントの事業課題の解決に最適ではないことがあるからです。
ヒアリングやディスカッションを進めていくと、本来解決したい課題はオウンドメディアでは解決できなかったり、目標達成までの期間や投資予算、またリソース状況によって、広告や現状施策の改善、体制の変更などのほうがよい解決策であると判断できるケースもあります。
実際、お問い合わせいただくうちの半分近くは、オウンドメディアをやるのではなく、別の方法で課題解決をしましょうとご提案するほどです。
そしてオウンドメディアをやると決めた場合、真っ先に考えることは、ターゲットとなるユーザーとどうやって接触し、事業課題を解決できるユーザーの態度変容をいかに起こすかということです。テクニック論だけでPVを伸ばし、オウンドメディアを成長させたとしても、それが事業課題解決に結びつかなければ何も意味がありません。
事業課題解決のために、どういったユーザーの態度変容を起こすべきか、そのためにはどういったコンテンツが必要なのか、それをどう届けるのかを考え、設計し、専念することが大切だと思っています。

また、短期的でなく中長期的な戦いが求められる自社所有のメディアだからこそ、様々な結果を生み出すことができるのがオウンドメディアの面白いところ。
たとえば過去に私が担当させていただいたクライアントで、法人企業をターゲット顧客とする、アウトバウンド営業が中心の会社がありました。1,000人以上いる組織で、テレアポがメインの営業活動であった会社だったのですが、ある事業部でオウンドメディアを立ち上げることに。
アウトバウンド営業が中心となると、売上を伸ばすためにはさらなる営業リソースの確保が必要になります。そこで営業活動の効率化のために、オウンドメディアを用いたリード獲得が目的でした。
そこでコンサルティングに入らせていただき、1年で月100件のリード獲得ができるメディアへと成長。さらにオウンドメディアに集まったユーザーを見て、他事業部へも展開できると判断し、ひとつの事業部で完結させるのでなく、そのオウンドメディアを活用したリード送客を、巻き込める事業部すべてへ展開していくべきだご提案させていただきました。
事業部のリード獲得だけでなく、数年後そのクライアント先の「アウトバウンドカルチャーを、インバウンドカルチャーにシフトさせる」ことを視野に入れて、一大プロジェクトに変えようと。
結果、10を超える事業を巻き込んでいくため様々な苦労がありましたが、翌年には月数百件のリード獲得、その翌年には月間千件を超えるリードを獲得し、様々な事業部のリードを創出していくこととなります。
そして徐々にインバウンドカルチャーが浸透していっていることが、外部の私から見てもわかるほどに。
もともと1名で始まったチームも、気づけば10人を超えるチームへ。また、当初のオウンドメディアだけでなく、様々なオウンドメディアが生まれ、管轄する事業部が増えていきました。少しずつ事業部ごとの成功事例を耳にするようになり、協力してくれる事業部も増え、経営陣も協力してくれ、文化の変革が起きていく――こうしたことは、集まったユーザーを見て様々な可能性を追い求めることができるオウンドメディアだから出来た事柄だなと思っています。
まずは目先の課題を解決することが重要ですが、ただそれだけを考えるのではなく、先々に起こる事柄を先に予見し設計したり、タイミングごとにさらなる可能性を考えたりするこがと、オウンドメディアの価値を最大化させていく上で大切なことだと思っています。
成功するまで踏ん張れず、運営終了するオウンドメディアが多い理由
ユーザー起点での施策を行っていれば、オウンドメディアが事業課題の解決に繋がるかというと必ずしもそうではりません。特に失敗してしまう企業の多くに共通するのが、成果が出るまでの期間を耐えきれないというケースです。
オウンドメディアを立ち上げて成果が生まれるまでには、様々な課題が発生します。たとえばトラフィックがまったく伸びない、最初に定めた成果が全く発生しないなど。そうすると決裁者はもちろん、運用メンバーのモチベーションも上がらず、社内に「本当にやっている意味があるのか」といった雰囲気になってしまうこともあるでしょう。
肌感を持ったプロジェクトを推進していくリーダーがいるとそんなことは起きないかもしれませんし、成果ではなく、運営していくことによる結果を見ていくことができますが、我々に依頼がくる時点でそんな状態ではないわけです。
またトラフィックが伸びているのに、なかなか成果に結びつかないといったことも珍しくありません。事業モデルにもよりますし、市場の過熱度にもよりますが、ある企業では1年半運営してやっと求めていた成果が出始めた、というケースもありました。
そして正しい施策を実施していても、成果がでるまでの期間を耐えきれずにメディアをクローズさせてしまう経営判断に至ったケースは実際によく耳にします。

オウンドメディアのプロジェクトを進めていくと、途中で様々な課題に遭遇するでしょう。そうした状況下でも、成果が出るまで耐え続けられるかがオウンドメディアでは重要なのです。
もちろん企業活動である以上、投資予算や使えるリソースは有限ですから、成果が出ないままずっと耐え続けることは容易ではありません。そこで私が大切にしていることは、成果が出るまでの最短ルートを辿っているかどうか、という視点です。
では、どのように最短ルートを見つけるのか、意識すべきは次の3つのポイントです。
オウンドメディアにおける、最短ルートで成果を出すための3つのポイント
1つは、適切なリソース配分に基づく戦略設計です。オウンドメディアは中長期的な戦いが求められるため、リソースをどこに投下すべきかという考え方が非常に重要です。
仮に競合他社がリソースも十分にあるのに対し、自社には限られたリソースしかないという場合、どこにリソースを集中させ、何をやらないかを明確にすること。そして、どういった戦い方をしていくのか、最低でも1年以上のイメージを持って進めていくことが大切です。
そのイメージがないと、都度対応でのリソース配分になってしまい、失敗してしまいます。たとえば予算の半分をオウンドメディアのサイト制作に投下してしまい、コンテンツ制作のための予算が限られ、良質なコンテンツ制作が難しくなってしまうといった本末転倒のケースは往々にして起こりうるのです。
またコンテンツSEOでよくあるのですが、なんとなく集めた周辺キーワードで戦っているケース。制作コストもディレクションコストも、つくった後のメンテナンスコストもかかってくるわけですから、ロジックのない “なんとなく” で集めたキーワードなんて一つもいらないわけです。
そういう事柄を一つずつしらみつぶしに対処していき、戦略設計面でも、体制面でも、最小リソースで最大成果が出るにはどうすべきかを考えていくことは、極めて重要です。
2つめは、運用フローの効率化です。非効率な運用は、そのまま成果が出るまでの期間を伸ばしてしまうことに直結します。これは当たり前のように思えて、本当に多くの企業で実際に起きてしまっている重要な問題です。
特にオウンドメディアでは、他事業部や他部署、外部パートナーとの連携が必要なケースも多いでしょう。大企業であれば、1本の記事を公開するまでに上長や広報などの様々なチェックフローがあり、その都度原稿ファイルの受け渡しを行っていき、気づけば記事公開までに1ヶ月半かかってしまったということもあります。
そうした運用において発生するコミュニケーションコストをいかに軽減させるか、その他プロジェクト管理にかかる工数をいかに減らすかは、成果発生までの最短ルートを辿るためには欠かせません。
ファイルのやりとりに4回コミュニケーションがかかっているとしたら2回でどう抑えるか、監修が2回入るならそれを1回に抑えるにはどうすべきか、そんな些細なところを詰め続ける必要があります。

最後に3つめのポイントとして、ただコンテンツを配信していこうではなく、成果最大化のために何をすべきかを常に考え続け、行動することです。
たとえばコンテンツによって訪れるユーザーの目的は違うわけですから、設置すべきCTA(Call To Action, 問い合わせや資料請求などユーザーに行動を促す要素)やコンテンツの役割は異なります。検索流入で考えた場合、 “オウンドメディアとは” というキーワードと “オウンドメディア 運用代行” というキーワードでは、調べているユーザーは異なります。なぜなら、そもそもオウンドメディアについて知りたいと思っている状態と、オウンドメディアの運用代行会社を調べている状態は違うからです。それにも関わらず、CTAやリンク先が同じというのは馬鹿げていますよね。
もちろんリソースやオウンドメディアの状態、またプライオリティなどで何をすべきかは変化しますが、そういったユーザーのことを考えれば当たり前のことを徹底して行い続けることが重要です。
たとえば過去、40万UUで2,000リード獲得していたオウンドメディアにコンサルティングとして3ヶ月入り、70万UU、4,000リードまで爆増したことがありました。実はそのオウンドメディアはそうした成果を出すポテンシャルはすでにあったのですが、まだまだ成果に対する思考も行動も弱かったことが課題でした。そこで、ただ適切な思考や行動についてお伝えしただけで、そのような結果に繋がったのです。
また、そういう行動ができない縛りを自ら設ける会社が多いなと感じています。たとえば「半年間は毎月何本記事を出す」といった縛りをつくっているケースが多いのですが、とるべき行動は都度変わるわけなので、それを行えばいいと最初から思考停止してしまうのは非常に危険です。
私はコンサルティングとしてプロジェクトに加わることがメインですが、時に運用をプロデュースすることもあります。成果が見えないクライアントワークですから、年間で具体的に何をするのかを示すことが求められがちです。しかし、必ず最初の3ヶ月の行動だけは提示しつつも、そこから先は予算だけ固定で何をするかは都度決めます、といった提案をしています。それは無意味な縛りをつくらないためです。
このように、私が大切にしているのは常に「この方法が本当に成果最大化に繋がるのか」と考え、行動し続けること、そしてその思考を停止させない状態をつくることにあります。
オウンドメディア立ち上げ時に愛用する3つのサービス
様々なツールを使いますが、今回は初期運用時に使用するツールを紹介できればと思ってます。ポイントは安くてシンプルなこと。
高いツールを最初から入れてもオウンドメディアが育ってなければ意味がないケースが多く、まずは運営するメンバーがいかにユーザー目線になれるのかのみを考えて、その感覚を身に付けることが大事だと思っています。なので、必要な機能をシンプルにくれるツールの中で、できる限り安いものを選んで使っていたりします。
高いツールを使うなら、安くにして、その分そのお金を運営に回そうよ、という感じです。
01. Ahrefs(エイチレフス)
『ahrefs』は、あらゆるサイトの被リンク分析や検索上位コンテンツ、想定流入キーワードを参考データとして調査することができるツールです。
適切なリソース配分が重要であるとお伝えした通り、競合他社と自社では投下できるリソースは異なります。そのため、「いかに競合に勝つか」という発想ではなく、「マーケットのどこを狙うか」「シェアをどう広げていくのか」という発想が大事であると考えます。
そこで『ahrefs』を用いて競合他社の状況から自社が狙うマーケットの理解を深め、目標とするマーケットのポジションに対して、どういったオウンドメディアを構築すべきかを設計するために用いています。
また、身近でなくイメージができない業界では、『ahrefs』を使ってある程度調べ、どのように戦っていくべきなのかの仮説を作るために使います。リンクの貼り方、アフィリエイトの割合、事業貢献のさせ方など、見ればある程度わかってきますね。
『ahrefs』はとてもリーズナブルな価格帯で、私が使っているのは1アカウント 179USD/月のスタンダードプランですが、オウンドメディアで考えるなら十分なデータを活用が可能だと思います。
02. Googleスプレッドシート
最短ルートを辿るためには運用フローの効率化が重要であるとお伝えしましたが、多くの企業で見落とされているのが、オウンドメディアのプロジェクト管理にかかる工数です。
たとえばプロジェクト管理をエクセルで管理していると、更新されたエクセルファイルの共有作業、また同時編集ができないことによる管理漏れなどが起こりえます。
また別のタスク管理ツールを使っている場合でも、多くのツールは使用用途以外の使い方ができないなど、オウンドメディアを進める上での十分な汎用性がないことがほとんどです。
そのため、私がコンサルティングさせていただくときは、セキュリティ上どうしてもNGの企業もありますが、大半がGoogleスプレッドシートでの管理を行っており、成果獲得までのプロセスや進行管理表、カスタマージャーニー、ペルソナ設計などの情報を含め、すべてを1つのGoogleスプレッドシートで管理しています。
また部署横断のプロジェクトの場合、部署ごとに管理方法が違うというケースも多くありますが、そういった場合は業務フローの見直しから行い、Googleスプレッドシートにてすぐさま変更、管理・進行できるフローへと整えていきます。
そうすることで、関わるメンバー全員がリンク1つでプロジェクトをスムーズに展開することができ、柔軟性の高いプロジェクト管理が実現、本来注力すべきコンテンツ制作に多くのリソース割くことができるようになるからです。
03. AWRcloud
最後にご紹介するのが、『AWRcloud』というキーワード順位調査ツールです。このツールの一番の良い点は、深く教えてくれない、かつ安いところ。
Google Analyticsでは、様々な数値が見れる一方、本来KPIとして追うべきでない数値も見えてしまうため、ついつい別の数値に惑わされてしまい、成果に繋がらない施策を立案・実施してしまうことになりかねません。
しかし『AWRcloud』は、「成果最大化のために必要な数値だけを追いかける」という目的に対して最適なツール。特に日々追いかけるべきキーワード別の検索順位を確認するのに適しており、またキーワードごとにグルーピングが可能なため、ビッグワード群、CVを狙うキーワード群などといった目的別の検索順位閲覧が容易にできます。また、情報閲覧する権限を招待でき、チームでシンプルに戦うのには適しているかなと。
自社のみ複数サイトで使うとしても99ドル/月、エージェンシープランで199ドル/月とリーズナブルな価格設定でありながら、複数人でアカウント共有が可能なため、チーム間での認識合わせにも最適なツールでしょう。
編集後記:オウンドメディアマーケティングの成功は、様々な変数の掛け算によって成り立っている
今回寺倉そめひこ氏にお話を伺い、特に印象的だったのは「いかに成果を最大化への最短ルートを辿るかが鍵である」ということだ。そめひこ氏が語る通り、多くのオウンドメディアが立ち上がり、そして同時に運営終了していくのを目にすることは珍しくない。
有限なビジネスリソースに対して、適切な選択と集中を行い、その上で成果に結びつくユーザー起点での施策を実施しなければ、たちまちリソースは底をつき、メディア閉鎖へと追い込まれてしまう。実際、本記事を読んで「失敗する前に知っておきたかった」と思われる読者もいるのではないだろうか。
そめひこ氏は最後にこう語る。
「オウンドメディアの成功は、様々な変数の掛け算で成り立っています。それは運営サイドの予算やメンバー等のリソース状況、事業領域、コンテンツ視点でのマーケット状況、そして社内事情含め、様々な変数によって掛け算が成り立っており、ひとつとしてその掛け算が同じオウンドメディアというのは存在しません。
つまり勝ちパターンが1つではないからこそ、自社の掛け算からどのような攻め方をすべきか、どういった勝ち筋を描くべきかを考える必要があるのです。
そして、ブレてはいけないのはユーザー起点で施策アイデアを出すということ。そこでこれからオウンドメディアを始めるという企業は、まずはスモールスタートで始め、ユーザー起点で行動する組織文化をつくることが大切だと思っています」

1987年、京都生まれ。藍染職人から2013年株式会社LIGに入社。同社でメディア事業部部長、人事部長を経て、2015年9月からは執行役員を務める。2016年3月にデジタルマーケティングカンパニー『MOLTS』を設立し、独立。オウンドメディア、コンテンツマーケティングのアドバイザリー、インハウス化支援、運用代行を軸にし、事業開発、営業組織教育、組織開発など幅広く支援の幅を広げ、累計50社以上の事業成長に貢献する。